「ナンバ歩き」を知っていますか?
西洋式の軍隊文化が入っていくる以前の歩き方で、
古来からの日本人の歩き方です。
最近では、アスリートの世界でも注目されていて、
為末大選手や高橋尚子選手が取り入れたことも有るそう。
そんな、ナンバ歩きを登山でやてみたら疲れないのでは?
と、いうことで実験してみました!
ナンバ歩きとは? 山岳民である日本古来の歩き方
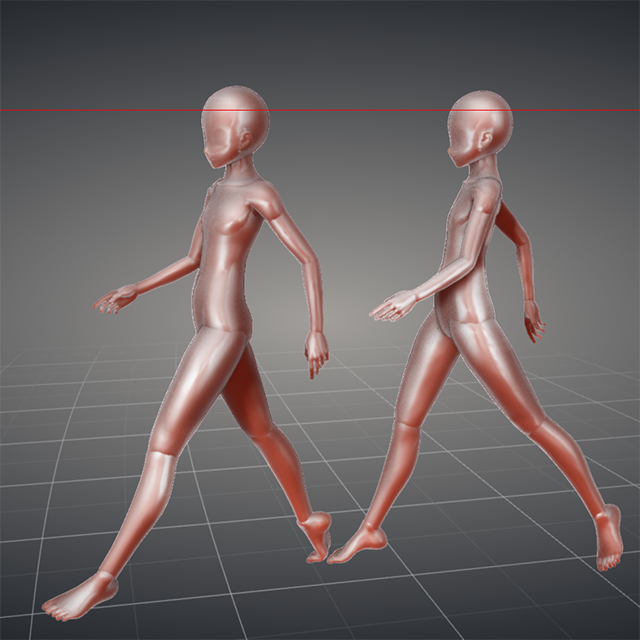
普段の歩き方は、右手と左手を出す方法ですよね?
図では、こんな感じ。
右足と左手を同時に出し、左足と右手を出して歩きます。
この歩き方は、明治時代の徴兵の際に海外から輸入された歩き方です。
ぶっちゃけ、かなり歴史の浅い歩き方ですね。
一方、ナンバ歩きは、山岳民族である日本人古来の歩き方。
右手と右足を同時に出し、次に左手と左足を同時に出して、歩いていきます。
図にするとこんな感じ。
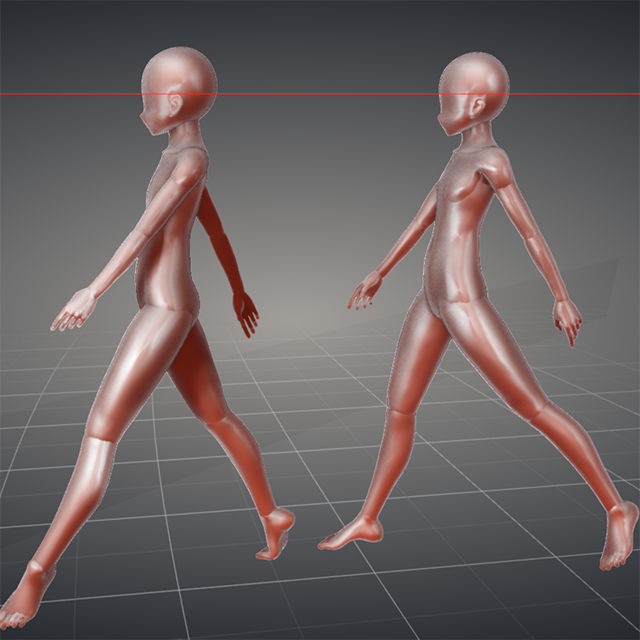
イメージとしては、力士のツッパリや空手の移動を伴った正拳突き、竹馬の要領です。
普段の歩き方は、体の中心に1本の軸があって、それを回転させながら歩いていますが、ナンバ歩きは、左右2本の軸を交互に動かします。
江戸時代までの歩き方がこれ。
袴がはだけない歩き方でもあります。
腕を組んで歩くと疲れないのはなぜなのか?

「腕を組んで登山すると疲れにくい! 」ってよく聞きますよね?
よく、山岳ガイドの方や登山上級者がやっています。
なぜ腕を組んで登山するのか?
それは、軸が安定するからです!
軸が安定することで、バランスを取るために使う体力を温存することができ、結果的に疲れにくくなるんです。
実際に腕を組んで歩いてみると、ナンバ歩きのように、左右2本の軸で歩くことが出来ますよ!
でも……
だったら、腕の振りも取り入れて、普通にナンバ歩き登山すればよくね!?
って思って、今回のナンバ歩き登山を試してみました。
自然とナンバ歩き登山をするためには?

さて、もっとも簡単にナンバ歩きをする方法があります。
それは?
ストックを2本使うこと!
右足を出すのと同時に右手のストックを出すだけで、
自然にナンバ歩きが出来るんです!
「右だけ出す」
「左だけ出す」
という簡単な意識付けで実践できるので、難しくありません。
それに、このようにストックの突き方を決めておくと、
ストックを突くリズムが狂いにくく、テンポ良く歩いていけます!
ストック1本だと、ストックを突くタイミングがなかなか掴めなかったり、
「右手と右足を出せばいい?」
「それとも右足と左手?」
と迷ってしまったり。
やはり、ストック二刀流がおすすめです!
ストック1本から2本にした時の感動の記事はコチラ
実際にナンバ歩きで登山してみた結果

さて、実際に実験してみました。
今回挑むのは急斜面で有名な男体山です。
ストックを2本用意し、右手と右足を同時に出して歩いていきます。
イメージは自分の両肩から腰まで、鉄骨が入ったイメージ。
全身を使ってバランスを取ります。
擬音語で表すとノッシノッシと歩くといったところ。
斜面が緩やかな部分ではどうなのか?
勾配が緩やかなところでは、確かな効果を実感できました。
今までの歩き方の場合、足場の悪い地面では、片足の足首でバランスを取ることになります。
今までは、片足が宙に浮いている間、片足の足首が小刻みに動いて均衡を保っていました。
しかし、
ナンバ歩きをすることによって、
歩幅が自然と短くなり、
体の軸が2本となったことで、バランスを取ることが容易になります。
体を大きく捻ることもないので、姿勢も維持しやすいです。
それに、今までの歩き方では、気がつくと腰から頭がさがっていて、自然と疲れやすい歩き方となっていました。
しかし、ナンバ歩きでは、頭だけが路面を見るために下がる格好になります。
腰から上はしっかりと垂直を保てるので、姿勢一つ取っても合理的な歩き方だと感じました。
急斜面の場合は?
ナンバ歩き試す?
……そんな余裕ありませんでした!
岩場は流石に辛いかな。
よじ登っていく感じだったし……。
使えるところは限られるね!
ザレ場の場合は?

感動したのが、ザレ場での山行です。
重心移動を大きくしてしまうと、滑りやすくなり、苦手な地形でした。
ですが、ナンバ歩きをすると、歩幅が小さくなり、滑りにくくなる事が実感できます!
勾配の小さなザレ場での歩行はおすすめですよ!
まとめ
登山中の疲れにくい歩き方は軸がぶれないことが大切。
そのために、日本古来の歩き方で有るナンバ歩きでの登山を取り入れてみた。
ストックを使うと自然と習得できる。
普通の斜面では確かな効果を感じる。
岩場はちょっときついかな?

